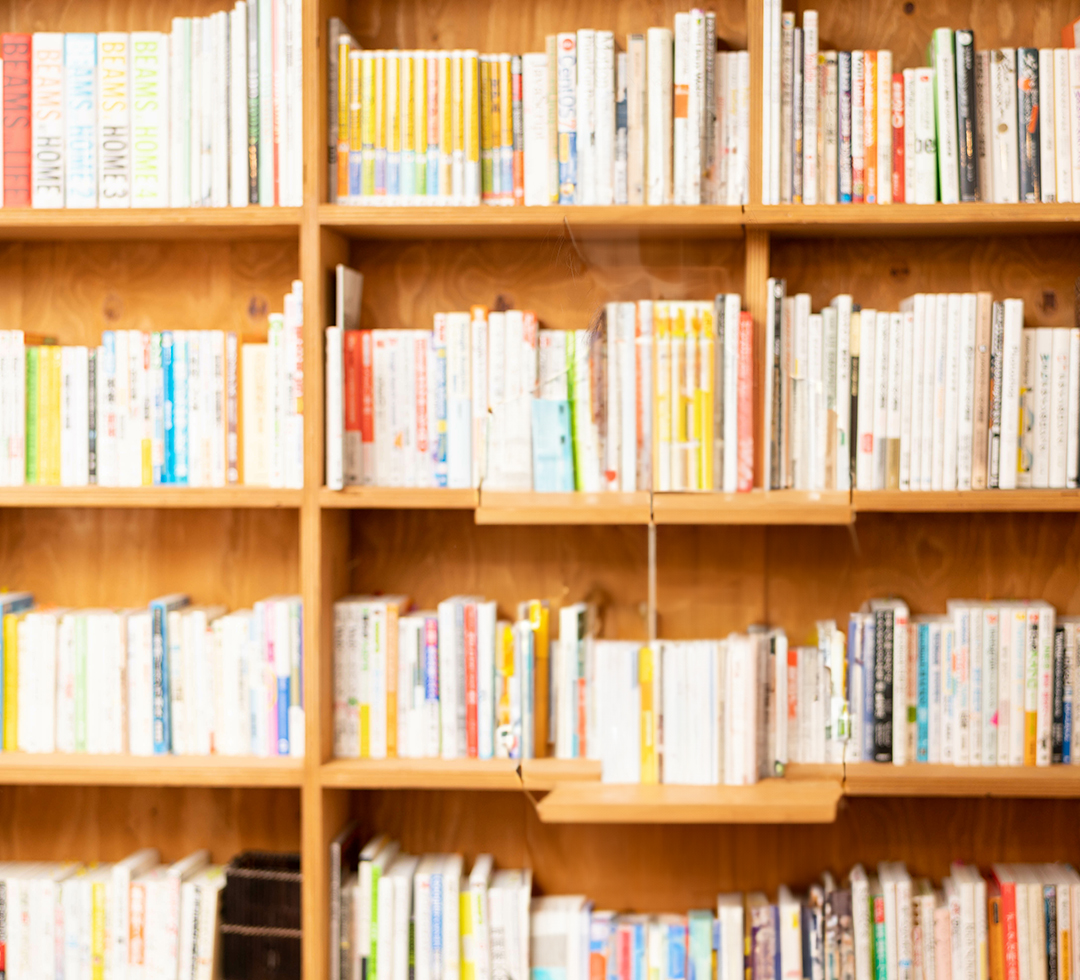オフィシャルブログ
相続した不動産は売却か保有か?
判断基準とメリット・デメリットを徹底解説!

親や親族から相続した不動産をすぐに売却すべきか、保有し続けるべきかは悩ましい問題です。
売却すればまとまった現金を得られますが、保有すれば将来的な資産価値の上昇や賃貸収入が見込めます。
本記事では、それぞれのメリット・デメリットと判断基準を詳しく解説します。
1. 相続した不動産をすぐ売却する場合
まずは相続後に不動産を速やかに売却するケースについて見ていきましょう。
【売却するメリット】
-
維持管理の負担を回避できる
不動産は所有しているだけで固定資産税や維持管理費がかかります。
遠方にある場合は管理が難しく、空き家の場合は倒壊や防犯面でのリスクが高まります。
早期売却でこれらの負担を回避できます。 -
資金をすぐに現金化できる
不動産は現金化しないと資産としては流動性が低いです。
売却すればまとまった資金が手元に入り、相続税の支払いや他の資産運用に充てることができます。 -
「空き家特例」で譲渡所得を最大3,000万円控除できる
被相続人が一人暮らしをしていた自宅は「空き家特例」が適用できる場合があり、譲渡所得から最大3,000万円まで控除されます。
ただし、相続から3年以内に売却する必要があります。
【売却するデメリット】
-
売却時に譲渡所得税がかかる
売却時には**譲渡所得税(20.315%)**と住民税が課されます。
ただし「空き家特例」や「取得費加算の特例」が適用できれば税負担は軽減されます。 -
市場価格より安くなる場合がある
相続後は早期売却を優先するあまり安値で手放してしまうケースがあります。
特に不動産市況が悪い時期だと損をする可能性があります。
2. 相続した不動産を保有する場合
次に、相続した不動産を保有し続けるケースを見ていきましょう。
【保有するメリット】
-
将来的な資産価値の上昇が期待できる
好立地の不動産であれば、地価の上昇や再開発の恩恵を受けられる可能性があります。
特に駅近や再開発エリアは将来価値が上がりやすいです。 -
賃貸運用で収益を得られる
不動産を賃貸に出せば安定した家賃収入が見込めます。
固定資産税や維持費を差し引いても手元に収益が残る場合は長期保有が有利です。 -
節税対策として活用できる
不動産は現金よりも相続税評価額が低くなるため、将来の相続税対策として有効です。
また、不動産所得があると所得税の節税効果も期待できます。
【保有するデメリット】
-
維持管理コストがかかる
保有している間は固定資産税や修繕費がかかります。
老朽化が進むとリフォームや建て替えが必要になる場合もあります。 -
空き家リスクが高まる
住まないまま放置すると空き家となり、管理負担や近隣トラブルが発生するリスクがあります。
また、空き家は税制上の優遇措置がなくなり、固定資産税が高くなる可能性があります。 -
将来の売却時に市場価格が下落する可能性がある
不動産価格は市況に左右されます。
長期保有しても必ずしも資産価値が上がるとは限らないため、売却タイミングを見誤ると損失が発生する場合があります。
3. 売却と保有の判断基準
売却か保有を判断する際は、以下のポイントを考慮しましょう。
-
立地と資産価値
駅近や再開発予定地 → 保有が有利
遠方や過疎地域 → 早期売却が有利 -
維持管理負担
近隣に住んでいて管理可能 → 保有が現実的
遠方で管理が難しい → 売却が有利 -
税金と特例の適用可否
空き家特例が使える場合は3年以内に売却が有利
将来の相続対策として活用したい場合は保有も検討
4. まとめ
相続した不動産は、維持管理の負担や税金、将来の資産価値を考慮して売却と保有を選択する必要があります。
「空き家特例」が適用できる場合は早期売却がお得ですが、賃貸運用で収益が見込める場合は保有するメリットも大きいです。
不動産の立地や状況に応じて、慎重に判断しましょう。