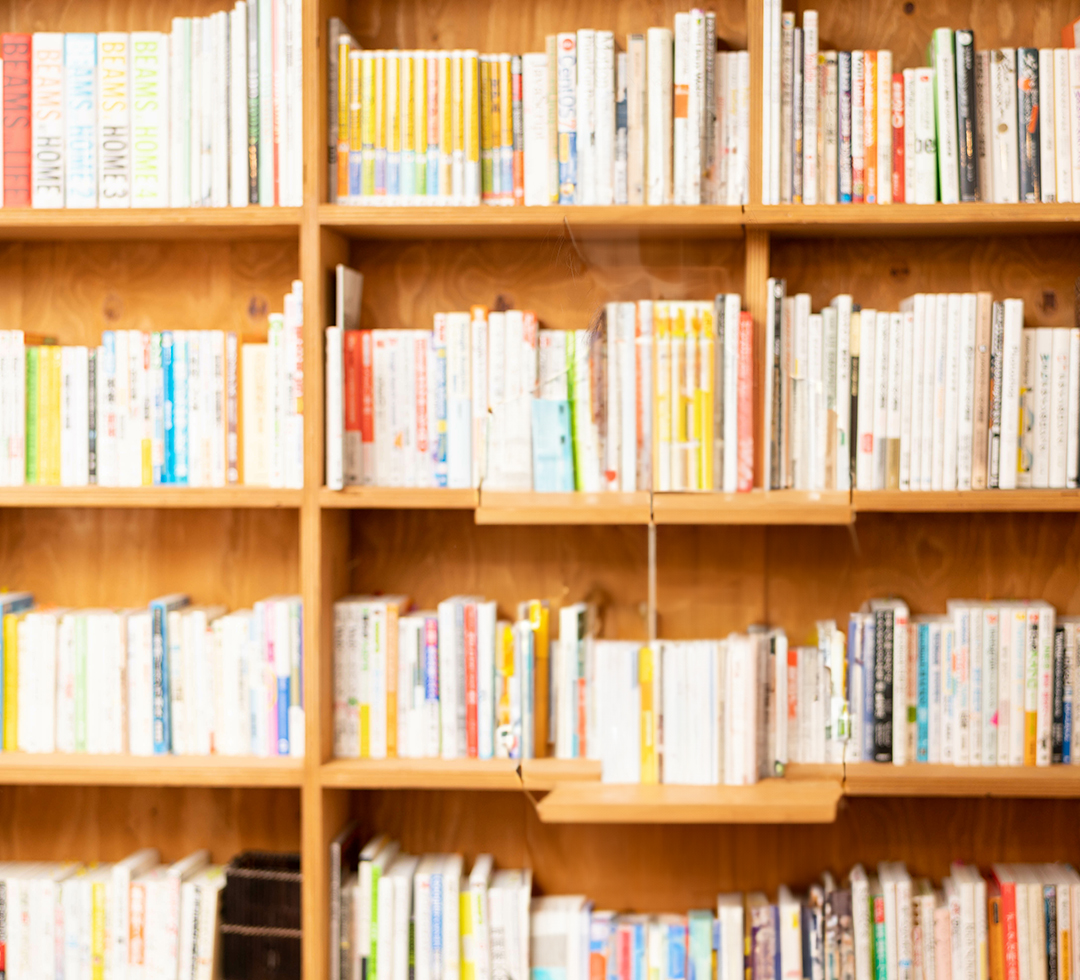オフィシャルブログ
遺産は葬儀費用に使える?
口座凍結や仮払い制度、実際の手続きと注意点

家族が亡くなった際には、遺族は悲しみに暮れる間もなく葬儀の手配を進めなければなりません。
しかし、葬儀費用は数十万円から数百万円と高額になるため、「故人の預貯金から支払いたい」と考える方は多いでしょう。
しかし、故人の死亡が銀行に伝わると口座は凍結されるため引き出しができなくなるのが原則です。
ただし、2019年7月の民法改正により「遺産分割前の相続預金の仮払い制度」が施行され、一定額までは引き出しが可能になりました。
本記事では、口座凍結後でも葬儀費用を支払う方法や仮払い制度の活用、相続税控除の仕組みについて詳しく解説します。
1. 口座凍結とは?
故人が亡くなると、銀行口座は自動的に凍結されます。
これは、不正な引き出しや相続トラブルを防ぐための措置です。
【口座凍結による影響】
- 預金の引き出し・送金が不可
- 公共料金やクレジットカードの自動引き落としが停止
- 定期預金や株式の解約も不可
ポイント
口座は、死亡届が役所に提出されると自動的に凍結されるわけではなく、銀行が死亡の事実を知った時点で凍結されます。
金融機関への死亡通知や新聞のお悔やみ欄で確認した場合に凍結処理が行われます。
2. 口座凍結後に葬儀費用を引き出す方法
① 仮払い制度の活用
2019年7月1日に施行された「遺産分割前の相続預金の仮払い制度」により、相続人は遺産分割が完了する前でも一定額まで預金を引き出せるようになりました。
【仮払い制度の内容】
- 引き出し額の上限:預貯金額の3分の1 × 法定相続分
- 1つの金融機関ごとの上限:150万円まで
例:故人の口座に600万円の預貯金がある場合
相続人が配偶者と子1人であるケース
- 配偶者の法定相続分:1/2
- 子の法定相続分:1/2
- 引き出し可能額:(600万円 × 1/3)× 1/2 = 100万円
- ただし、150万円が上限なので、仮に預金が1,000万円以上あっても引き出しは最大150万円まで
【必要書類】
- 故人の死亡診断書
- 戸籍謄本(故人と相続人の関係がわかるもの)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
注意点
- 金融機関ごとに上限額が設けられているため、複数の銀行に口座があれば合計で150万円以上の引き出しも可能です。
- 葬儀費用以外にも使えるため、医療費や生活費にも充当できます。
② 預金だけ先に遺産分割協議を行う方法
仮払い制度で引き出せる金額では足りない場合は、預金のみ先行して遺産分割協議を行う方法があります。
【手順】
- 相続人全員で協議を行い、預金だけを先に分割する旨を決定
- 協議内容を「預金に関する遺産分割協議書」に記載
- 協議書を金融機関に提出して預金を引き出す
ポイント
- 相続人全員の同意が必要ですが、手続きがスムーズに進めば預金を早期に引き出せます。
- 他の遺産(不動産や株など)の分割協議は後回しにできます。
3. 葬儀費用を相続財産から精算する方法
相続手続きが完了した後であれば、葬儀費用は相続財産から精算可能です。
【手順】
- 相続人が一時的に葬儀費用を立て替える
- 銀行口座の凍結解除や遺産分割協議が完了した後に精算
- 葬儀費用は相続財産から差し引いた上で分割
注意点
- 領収書は必ず保管しましょう。
- 相続人同士で精算方法を協議し合意する必要があります。
4. 相続税申告で葬儀費用は控除できる
葬儀費用は相続税計算時に債務控除の対象となり、課税額を減額できます。
【控除対象の費用】
- 葬儀社への支払い費用
- 火葬料・斎場使用料
- 僧侶へのお布施
- 通夜・告別式費用
【控除対象外の費用】
- 香典返し・会食費用
- 墓地や墓石の購入費用
ポイント
- 相続税申告書に葬儀費用を記載し、領収書を添付することで控除が認められます。
- 正確に申告すれば相続税を節税できます。
5. 生前対策で口座凍結を防ぐ方法
① 家族信託の活用
- 生前に財産を信託し、家族が管理できるようにしておくと相続後も柔軟に資金を引き出せます。
② 生前贈与や共同名義口座に変更
- 故人名義だけでなく家族名義の口座にも資金を移しておくと、口座凍結時に引き出せないリスクを防げます。
6. まとめ
葬儀費用は基本的に遺族が一時的に立て替える必要がありますが、2019年7月施行の仮払い制度により金融機関1行当たり最大150万円まで引き出せるようになりました。
また、仮払い制度で不足する場合は、預貯金だけ先行して遺産分割協議を行う方法も選択肢となります。
さらに、葬儀費用は相続税の控除対象となるため、申告時には領収書を添付して節税につなげましょう。